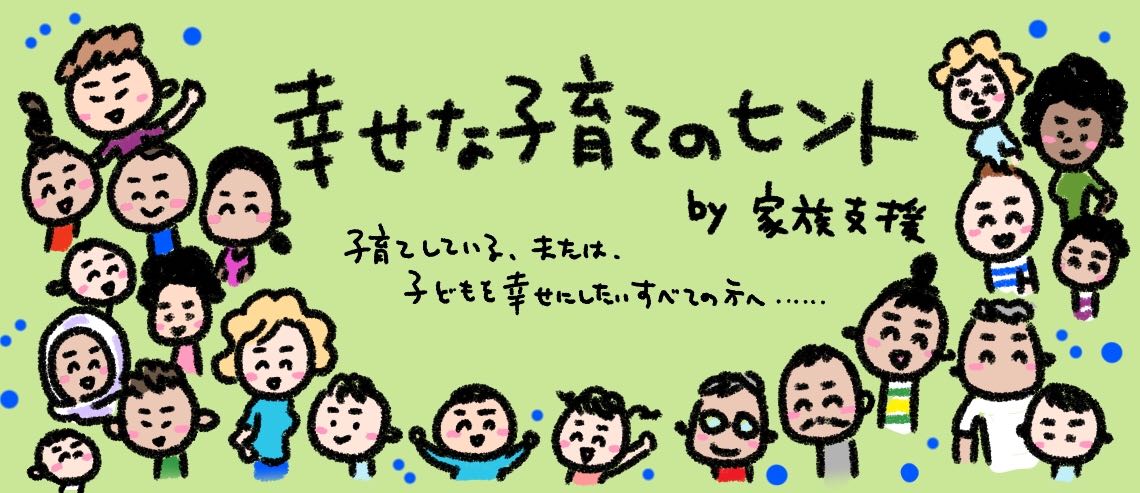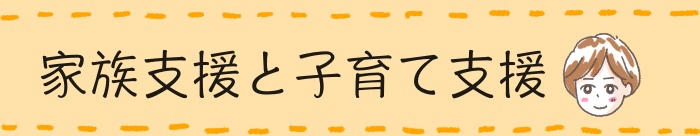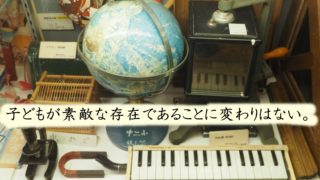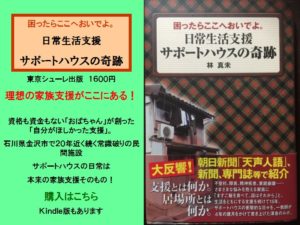「子どもの人権」がだいじ っていうムーヴメントが、日本の子育てを間違った方向に連れて行っちゃうんじゃないかって、心配しているんです。
Contents
人権は子どもも大人も関係なく全員に
本来は、大人だろうと子どもだろうと人権が守られているのは、あったりまえのこと。
言葉に出すまでもない、自明の理っていうやつ。
でも、なんなら、日本は、大人のほうが、人権が守られていない場面がいろいろあるんじゃないかな。
卑近な例で言えば、先生の人権。
違法労働に該当する働き方はずっとそのままだし、子どもに罵倒されても怪我を負わされても泣き寝入り。
自分たちの人権がこのように守られていない状況の中で「子どもの人権を守りなさい」っていう研修を受け、それに邁進するっていうギャグのような展開が現実に繰り広げられています(笑)。
きっと、それぞれの場で似たようなことはあるのではないでしょうか。
それなのに、なぜ「子どもの」人権ばかり、問題にされるんだろうなあっていつも思います。
もちろん、悪いことばかりじゃなくて、基本的には、安全で過ごしやすいこの国で暮らすことで、私達はちゃんと人権を守られている側面もあると思います。
そもそもの子ども観/人間観が違うから
子ども観
わざわざ「子どもの人権」と子どもの人権だけ特別に扱う発想って、おそらく西洋由来のものだと思うのです。
私は西洋人じゃないから実感としてわかっているわけじゃないけど、文献資料によると、たぶんそこには、西洋で子どもを大切に扱ってこなかった歴史が影響しているのではないかと。
その点、日本は子どもを大切に可愛がって育ててきた歴史がある。遺伝子に組み込まれたその感覚の上に「子どもの人権」を乗せちゃうと、なんだか盗人に追い銭的な状態が生まれちゃうんじゃないかと思って、それを心配しています。
人間観
スイスに長く暮らした、著名な心理学者・河合隼雄氏の”「個」の論理・「場」の論理”論を知ると、日本と西洋の違いがよくわかります。ざっくり言うと、日本は「個」よりも「場」(職場や学校、家族などの組織やグループ、人間関係全般)を大切にし、西洋は、「個」(自分やひとりひとり)を尊重する。「場」を優先する日本が、「個」を優先する西洋の倫理観を輸入したから、混乱が起きている、という指摘です。1980年代の論だけど、慧眼ですよね。
たぶん、いまだに日本はそれに苦しんでいる……。
たぶん「友達家族」の概念が生まれ、広まったのは70年代くらいだと思います。それまでの価値観(戦前の、男女または親子の厳格な上下関係)を壊したいというムーブメントが、それまでのような親子の上下関係を否定したかったのではないかと。
そして90年代以降、子どもを大切にする風潮が高まり、今度は、上下逆転し、子が上で親が下という関係の親子が多くなったように思います。
もちろん、俯瞰で見れば、そういう時代の流れとは関係なく、厳格ではない、お互い話し合う空気のある、民主的な親子の上下関係の家族も多いとは思います。
でも、体感として、親子の理不尽な上下関係は少なくなった反面、子が上で親が下の逆転関係の親子、またその傾向がある親子がじわじわ増えている気がします。
声を聞かれ過ぎて迷う子ども達
「子どもの人権」そして「子どもの意見表明権」の御旗のもと、
「あなたはどうしたいの?」と子どもに聞くのが最善だという空気感を感じるのは、私だけでしょうか。
どっから見ても正しそうな空気だけど、実態に即して考えると、これにはちょっとした違和感があるのです。
考えてもみてください。
たぶん、健全な親子関係のなかで育っていたら、こんなことを聞かれるシチュエーションはないのではないかと。
そんなこと聞かれるまでもなく、したいことがあったら親に普通に言って、普通に対応されて暮らしてる。
だからわざわざそれを改まって聞かれることもない。
それを聞かなきゃいけないシチュエーションがあるってことは、なにかしら特別なケースなのでは?
そしておそらく、それを聞かれるシチュエーションにいる子は、それを聞かれても、答えを持ち合わせていないことが多いんじゃないかなあ。
不登校の子に「あなたはどうしたいの?」って聞いて、「ゲームしたい」っていう子どもの意見を尊重して「ずっとゲームさせてあげなさい」って児童精神科医に言われてその通りにしたっていう話を聞きました。
あれです、エネルギーが溜まるまで好きなことをさせてあげましょうっていうやつです。
けど、そのシチュエーション、ホントのホントの心の奥からゲームしてハッピーって思っているかなあ……。
ゲームをすることで現実から逃げられるから、辛すぎるときの慰みには必要かもしれないけど……。
それって「子どもの人権」「子どもの意見表明権」を尊重することと同義ですか?
「ゲームしたい」は、私は、本当の深い答えじゃないと思うし、かといって本当の深い答えは見つからない。そんな状況で、「あなたはどうしたいの?」って問い続けることは、むしろ子どもを追い詰める結果にならないかなあって思うのです。
逆に、「こうしなさい」って大人に言ってもらえることで救われる子もいるんじゃないかなあ。
我慢する人権・怒られる人権・辛い思いをする人権を奪うな
「子どもの人権」が行き過ぎると、かえってネガティヴな経験をするチャンスを奪われるという現象も出てくるのではないかと。
もともと子どもを大切にする文化を持つ日本人が、人権なんてあったりまえのことをことさら意識するあまり、子どもを大切にし過ぎて、成長にぜったい必要な“辛い”“しんどい””我慢”を経験するチャンスを奪ってしまうのでは、と心配しています。
親がわからずやとか、友達がわがままとか、勉強が難しいとか、とにかくうまくいかないことや理不尽な思いをすることがないと、それを乗り越えるチャンスがない。なにか難しいことを乗り越えた経験がないと、いつまでも自信が持てない。自信が持てないと、挑戦ができない。挑戦ができないと失敗もできない。失敗がないと成長ができない。成長するっていうのは、子どもにとってかけがえのないこと。それこそ、成長を阻むなんて、「子どもの人権」の大いなる侵害です。
風が吹けば桶屋が儲かる論法だけど、そういうことです。
私がずっと言い続けている、子どもの「マイナスの体験を大切に」っていうのは、つまり、こういうことなんです。
「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざは、一見関係のない出来事が連鎖して、思いもよらない結果をもたらすことをたとえる言葉です。具体的には、風が吹いて砂埃が立ち、それが原因で盲人が増え、盲人が三味線を弾くようになり、三味線の皮に猫の皮が使われるため猫が減り、猫が減るとネズミが増え、ネズミが桶をかじるので桶屋が儲かる、という一連の流れを指します。(AIによる説明)
昭和/平成の恨みを令和で晴らすな
もうこれは、誰も言ってない自説に過ぎないから、読み飛ばしてほしいのですが、私は密かに「子どもの人権」に惹かれる人は、無意識に、自分自身のインナーチャイルドの痛みを癒したいのでは、と思っておるのですよ。
おそらく私もその一員でした。
でも、それはそれで個々がやることであって、令和の子どもを巻き込むなって今は思ってる。
前の項でずーっとつらつら訴えてきたように、そのことが子育てを混乱させていないかなって思ってしまったから。
実際に子ども3人育て、その後、学校で毎日たくさんの子どもとまみれているうち、あの頃の私が使っていた「子ども」という言葉は、実体のない集合名詞だったんだなーと、今は思うようになりました。
いつも言ってるけど、現実は一筋縄ではいかない。イメージと事実は違う。
実際のひとりひとりの子どもは本当に様々で、現実には「子どもの人権を守る」という観念を超える実態がある。
くりかえすけど、人権が守られるのはあったりまえのこと。その上で、子どもと本気でいっしょにやっていくと、その現実の前には「子どもの人権を守る」っていう主張が、薄っぺらく感じてしまう。
「子どもの人権を守る」は、大人の言葉だなあと思ってしまう。
ほとんどの子どもは、それとは関係のないところでに元気に生きている。
もっと子どもを信じてほしい
「子どもの人権」だけじゃなく、「子どものため」にアクションする人達って、もしかして究極的に子どもを信じていないんじゃないかって思うことがあります。
私も、子育てや子育て支援をしているだけでは気づかなかった。
けれど、学校の先生になって、毎日たくさんの子ども達と一緒にいることで見えてきたことがあります。
うまく言えないけど、というか言葉に変換すると陳腐になっちゃうんだけど、子どもは大人がどうこうしてあげなくちゃいけない存在じゃないんじゃないか、と思うんです。
もちろん、身動きできなくなって助けが必要なこともあるとは思う。大人が教えるべき規範もある。
でも基本的に、子どもは自分の力で立って歩いて行く。
そんな感じ。
「子どものため」のアクションの多くは、その子どもの目に見えないパワーを信じていないんじゃないかって感じます。
なんていうかなあ。「子どもはすごい」「子どもはすばらしい」と言いながら、子ども自身の力を信じていないから、「守ってあげなきゃ」「良い環境を与えなきゃ」って思うんじゃないかと。
全部がそうだとは言ってませんよ。
でも本当に、よくよく考えないと、気をつけないと、子育て教育業界には耳障りの言い美しい謳い文句が溢れているから……。
○人権が守られるべきなのは、言うまでもなくあったりまえ
○家族が民主的な上下関係を保って普通に生きていれば「子どもの人権」の心配はいらない
以上の論説は、いろいろな独学の果ての私の考えなのだけれど、”エビデンスベース”より、たぶん当たってるはず。
(家族支援@学校 同時掲載)