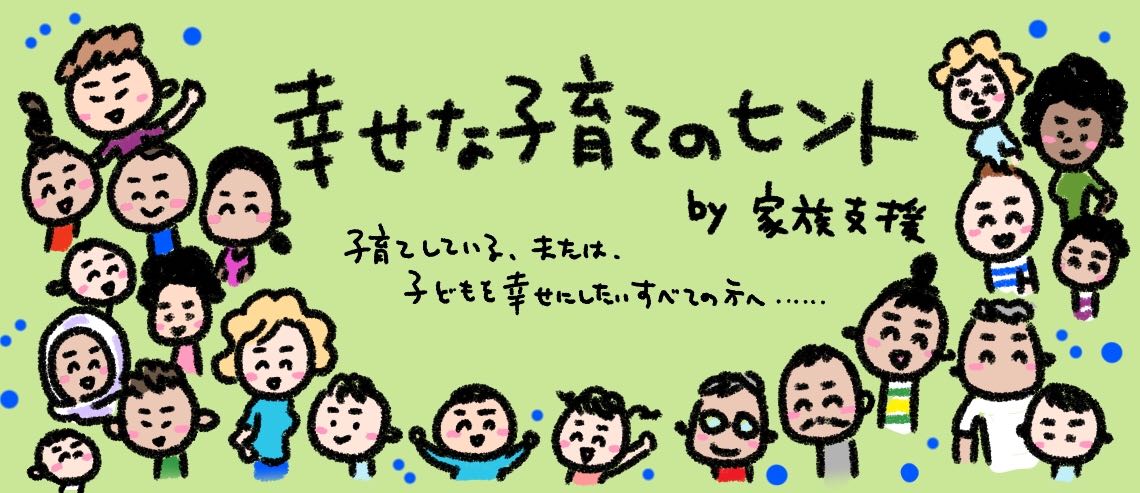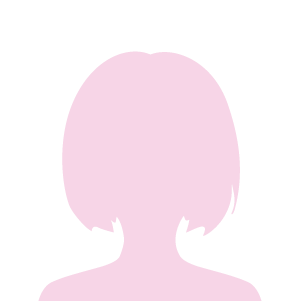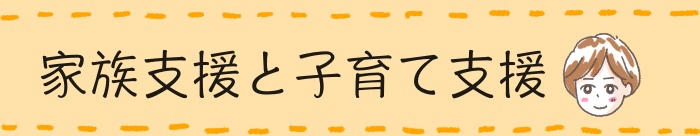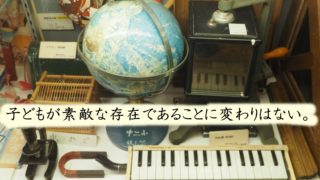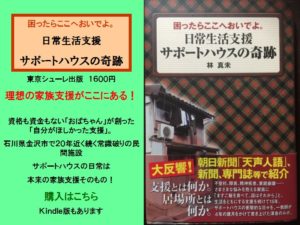不登校を考える その1では、不登校の原因について考えました。
不登校を考える その2では、不登校にアプローチするアクションについて考えます。
子どもが不登校になると、多くの親はまず大きなショックを受けます。そして学校と相談しながらなんとか登校させようとする。けれどうまくいかずに、葛藤しながら、この状態を認めなくてはいけないと思うようになる。自分を責めたり、学校を責めたり、子どもを責めたりしながら……。(私は、アクションする人ー教員、カウンセラー、ソーシャルワーカー、支援者(当事者出身も含めて)などーは、この親の苦しみを自分の痛みとして感じていなければいけないと思います。)
子どもが学校に行かなくてもまーったく気にならないという人は稀だし、家にずっといるのは子どもの成長にとってベストではないとほとんどの人が思っています。当事者も学校を含めた支援者も、「なんとかしたい」と思う。でも、なかなかうまくいかない。そんな状況に、少しでもヒントになればと思って、知識と経験を総動員して、一所懸命考えてみます。
支援はオーダーメード
不登校を考える その1で言及したように、不登校の原因はいろいろ。それに加えて、子どもの個性も一人一人違うし、家の考え方や家族構成もひとつひとつ違う。
そうなると、不登校だからこうすればいいなんて簡単に言えるわけはない。
私は、よくあるケースというのはある思っているけれど、それが全てじゃないから、究極的には、一つ一つのケースにそって考えていくしかない。
たぶん、必要な支援は一つ一つの家庭で、少しずつ違う。
どうしても、家族、子どもという大きな主語、不登校という大きなくくりで考えがち、言いがちなのだけれど、これが基本中の基本であることを、まずはしっかりおさえたいです。
アクションのいろいろ
今現在、行われているアクションを羅列してみると、
・教員(担任/学年主任、校長/副校長/教頭)との教育相談
・学校での対応(保健室登校、別室登校、親子登校、短時間登校など)
・行政機関や支援機関での相談
・スクールカウンセリング
・スクールソーシャルワーク
・民間カウンセリング
・コーチング
・フリースクール
・ホームスクーリング
・復学伴走サービス
・引き出しサービス
・セルフヘルプグループ
・オンラインサロン
・SNSコミュニティ
・不登校特例校
・通信制高校
こんな感じですかね。まだあるかな?
それぞれの詳細については、インターネット上にいやになるくらいたくさん情報があるので、ここでは繰り返しません。
ただ、ここで言いたいのは、これらは主に不登校へのアクションだということです。
不登校を考える その1で解説したように、私は不登校を症状と捉えています。症状は表に現れたもので、それにはなにかしらの原因がある。
不登校に対してアクションするというのは、医療に例えると対症療法です。
でも、必要なのは、最適なのは、根治(または寛解)ではないのかな、と思っています。
アクションの盲点
アクションのいろいろで羅列したさまざまな支援は、玉石混合です。もしかしたら、”石”のほうが多いかも。
これはほんとに気をつけてほしいのですが、無償か有料か、学校・公的機関か、民間・ボランティアによるものか等の外形では、効果的なアクションができるかどうかなんて、全くわかりません。「あそこは良い相談機関だ」「このメソッドが素晴らしかった」という友人知人の評判も、あてになるかどうかわかりません。
担当の先生だから目の覚めるような素晴らしい不登校対応ているとか、カウンセラー、ソーシャルワーカーは有資格者だから信頼できるとか、逆に当事者のアドバイスのほうがいい、とか、それもわからない。わからないというのは、全部だめという意味じゃない。
とにかく、どこにいても、誰であっても。
だいじなのは、人なんです。
どこの誰が有効な支援を提案できたり、不登校の親に伴走してくれたりするかは、出会ってみないとわからない。
今、子どもの不登校で悩んでいるのなら、良い出逢いに恵まれますように。
少し前は、情報がなさ過ぎて困っていたんだけど、今は情報がありすぎて困るな……。
アクションの大きな二つの流れ
アクションのゴールの究極は、子どもの自立、そして子どもの幸せだとは思うんだけれど、それをもたらすものが何なのかで、意見が分かれています。かたちとしては様々ですが、アクションは、概ね二つの流れに分けられると思います。
その二つとは、
・再登校を目指して、それに向かうやり方
・子どもの思いに傾聴、共感して、現状を肯定するやり方(再登校を目指さない)
です。
・再登校を目指して、それに向かうやり方
私は、不登校になっても、かならずしも再登校を目指さなくてもいいと考えます。
この考えは、・子どもの思いに傾聴、共感して、現状を肯定するやり方に近そうですが、そうではありません。
上記、参考リンク記事の最後で、私は、注目すべきは、不登校かどうかより、「「自分は生きているだけで価値がある」という確信、「世の中は学校だけじゃない」という視野、そして、「いい人はたくさんいて、人生はなんとかなる」という楽観。」と書いています。
でも、あらためて考えてみたら、そもそも、そんなメンタルの子は不登校にならない。その考えを持ち合わせていないから、不登校という症状が出ているわけで。もし、その考え、あるいは、言葉は違っても似たようなメンタルに至ることができれば、自然と再登校という結果がついてくるはず。そう、原因が治ったら、症状は消えるというわけです。
だから、私の考えは、どちらかといえば・再登校を目指して、それに向かうやり方に分類される。もっと正確に表現すると、不登校の原因を突き止めてそこにアプローチするので、結果的に再登校に至るという感じかな。
・子どもの思いに傾聴、共感して、現状を肯定するやり方
このやり方は、一見、子どもの心に寄り添った良いやり方に見えるけれど、実は、根治から遠ざかる方法ではないかと心配しています。子どもの思いをよく聴くことで、子どものメンタルにアプローチできて、子どもが幸福になれば、もちろんそれに越したことはありません。けれど、失敗例も多いから……。
子どもの思いをよく聴くことはだいじです。
でも、子どもの人権に騙されないでで書いたように、答えられないときに「あなたはどうしたいの」と聴かれ続けるのは、むしろ苦痛を強いることです。
そして、子どもが言ったことが、そのまま真実とは限らないことにも気をつけないと。
つまり、このやり方は、子どもを安心させられたり、子どもと対立しなくてすんだりするけれど、一方で、子どもの状況を固着させたり、状況を見誤ったりする危険もはらむのです。
私は、子ども達は、できれば元の学校に、あるいは(可能であるなら)転校して他の学校に、学校にだめならフリースクールでもどこでもいいから、とにかくどこかへ通うべきだと思います。
家にずっといてはいけない。
これは教師としての嗅覚、生物としての本能レベルでそう思うのです。
それに、子どもの心の奥底の願いもおそらくそれだと思います。子どもの口から、けっして言葉として紡がれなかったとしても。
とはいえ、部屋から出てこない子を無理やり引きずり出して連れて行くのも違う。
必ず、本人が自分の意志で自分の足で、学校やその他の場所に行くことがだいじです。
というわけで、不登校を考える 3では、今(2025)いちばん多いパターンの不登校はどんなもので、それを具体的にどうすればいいのか、について考えてみようと思います。
(家族支援@学校 同時掲載)